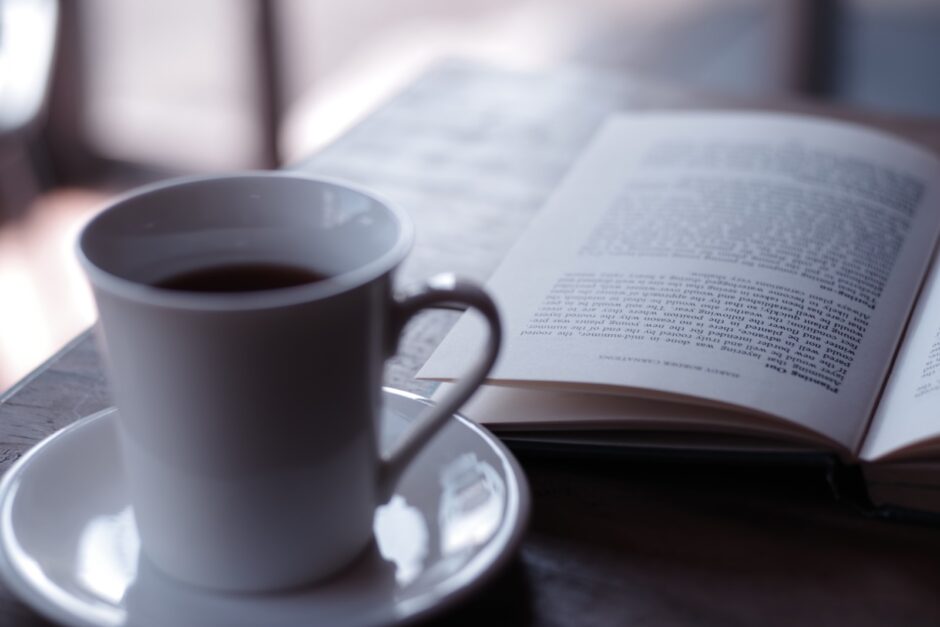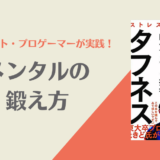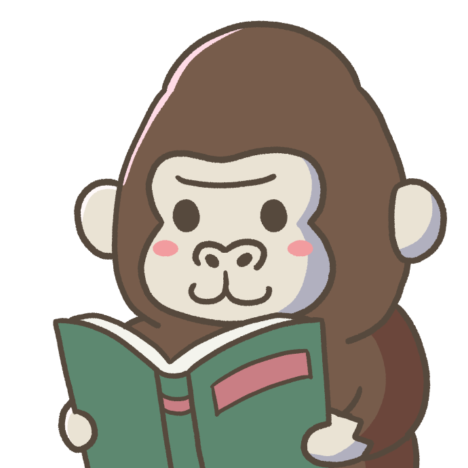
司馬遼太郎『坂の上の雲』を読みました!
日清・日露戦争を題材にした小説です。
私が敬愛する、ライターの田中泰延さんがおすすめしていたので読みました。
恥ずかしながら、いままで司馬遼太郎さんの作品は読んだことが無かったんです。時代小説は池波正太郎さんの剣客商売ぐらいしか読んだことが無かった・・・。
文庫版全8巻の大作ですが、あっという間に読めます。
もくじ
坂の上の雲はどんな小説?
日露戦争を勝利に導いた秋山好古・真之兄弟。俳句改革に命をかけた正岡子規。 伊予松山出身の3人を中心に、明治という時代の明暗と、近代国家誕生にかけた人々の姿を描く、不滅の国民文学。全8巻。
Amazon商品紹介より抜粋
明治時代の、日清・日露戦争を描いた長編小説です。
主要な登場人物は3人。
一人目が、秋山好古。愛媛県生まれです。陸軍士官学校を卒業し、明治20年フランスに留学。日清・日露戦争では騎兵部隊指揮官として活躍しました。日露戦争では、当時のロシアで最強と言われた騎兵集団と戦い、打ち破った功績があります。
二人目は、秋山真之。好古の弟です。海軍兵学校を卒業し、明治30年にアメリカに留学。日露戦争では連合艦隊の参謀となり、様々な作戦を編み出しました。日露戦争では日本海海戦において、ロシアのバルチック艦隊を破ったことが有名です。「本日晴朗ナレド波高シ」の名電文の発案者でもあります。
三人目は、正岡子規。秋山兄弟と同じく愛媛県松山に生まれました。秋山真之は、学校の同級生であり、友人です。俳句、短歌、詩、小説などの創作活動を行い、日本の近代文学に影響を与えた人です。
この三人を中心として物語が進行します。
明治時代は、それまでの日本の生活が一変した時代でした。当時、弱小国とされた日本が、いかに中国(清)・ロシア帝国と戦い、勝利したのかを描いています。
『坂の上の雲』の感想~大国との戦いに挑む、熱い人間ドラマ
本作は秋山好古の出生から始まり、亡くなるまでを描いています。
正岡子規は出てくるけれど、スポットライトが当たるのは前半だけ。小説の半分以上は、日露戦争の描写です。
この作品を読むまで、実は日露戦争についてロクな知識がありませんでした。それこそ高校の教科書で読んだぐらいの知識しかなかった。歴史の教科書の、1ページにも満たないような部分だったと記憶しています。
しかしながら、本作を読んで、この戦争が当時の日本にとってどんな意味を持っていたのかを知ることができました。恐らく日露戦争に日本が勝利していなかったら、わたしたちの国は今とは全く違う形になっていたはずです。
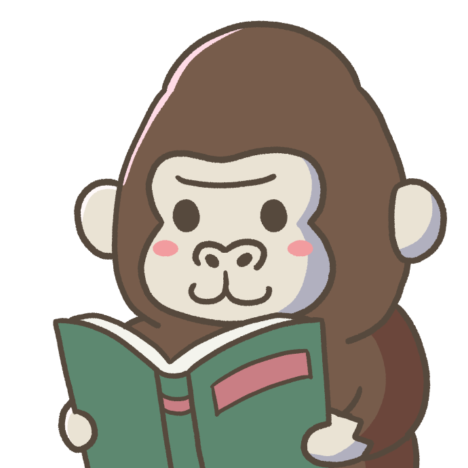
北海道あたりはロシア領になってたかも。
しかしながら、当時の日本とロシアでは国力に差があり、冒険的要素が非常に強い戦いでした。勝ち目が少ないにもかかわらず、なんとか勝率を六分ぐらいにしようと、当時の人々がもがいていた姿が描かれています。
兵の数も足りない。軍艦も劣っている。
それでも日本が勝利できた理由は、一つは日本のち密な作戦であり、もう一つはロシア自身の混乱でした。
要するにロシアはみずからに敗けたところが多く、日本はそのすぐれた計画性と敵軍のそのような事情のためにきわどい勝利をひろい続けたというのが、日露戦争であろう。
司馬遼太郎『坂の上の雲(八)』より
本作ではロシアと日本の両面から、当時の戦争を詳しく描いています。特にロシアの姿からは、現代にも活かせる教訓を沢山得られました。上が無能であれば、下が苦労する。こんな風にはなりたくない。
最後のシーンである、日本海海戦におけるバルチック艦隊との戦いは必見ものです。手に汗握る展開と描写が激熱。鳥肌がたつぐらい興奮しました。
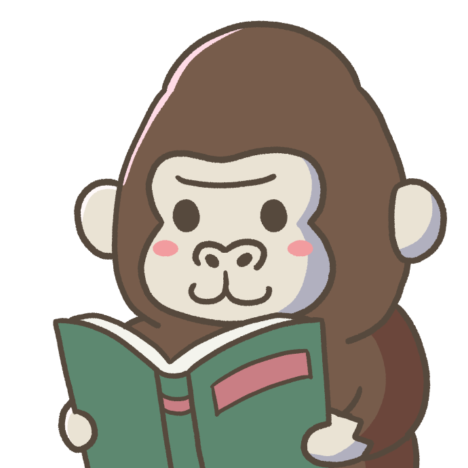
東郷ターン!!!!!
ライター目線で見る、司馬遼太郎のすごさ
私がこの本を読んだきっかけは、ライター田中泰延さんの書籍『読みたいことを、書けばいい。』です。
本書で田中さんがおすすめする書籍の中に、本作『坂の上の雲』が入っていました。
「文章を書くために役立つ本」のお墨付きを貰っていましたが、確かにその通り。
司馬遼太郎は、まさに調べることの達人のような作家でした。
『坂の上の雲』の作中で、著者自身の考えや登場人物に関連する雑学が出てきます。それが、どこで知ったんだそんなんと言いたくなるような細かいことばかりです。
≪司馬遼太郎の資料蒐集の徹底さについては、多くの人が感嘆の声を上げている。神田の古書街からある日、ひとつのテーマの本がいっせいに消えるんです。どうしたのかと思うと、司馬先生が今度こういうテーマで書くからと各店に撒を飛ばして、資料がトラックで東大阪の司馬先生の家へ運ばれたあとなんです≫
雑誌『サライ』平成16年通巻373号
ライターは、調べることが九割九分九厘 とは田中さんの言葉です。
魅力的な文章を生み出す人は、調べる量も段違いであるというのが分かります。『坂の上の雲』の登場人物がこんなにもイキイキとしているのも、臨場感たっぷりの戦闘描写に興奮するのも、すべては作家司馬遼太郎の調査の賜物でしょう。
とにかく説明することは難しいけれど、一度本作を読んでみて欲しい。司馬遼太郎さんの凄さが分かります。
ライターを名乗るからには、「いつも心に司馬遼太郎」を胸に秘めて、活動したいと思います。