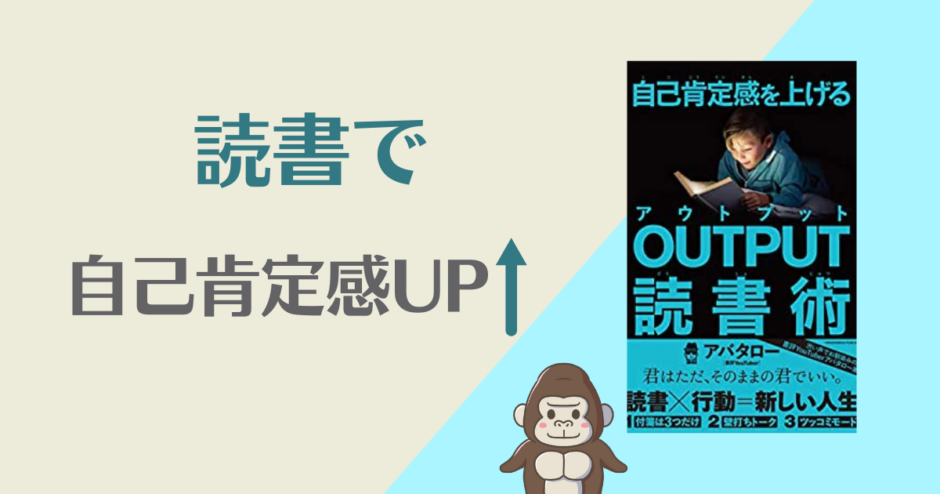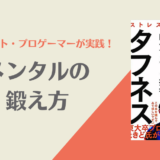読書が好きだけど、知識が身についていない気がする。どうすれば学んだ内容を忘れないでいれるかな?
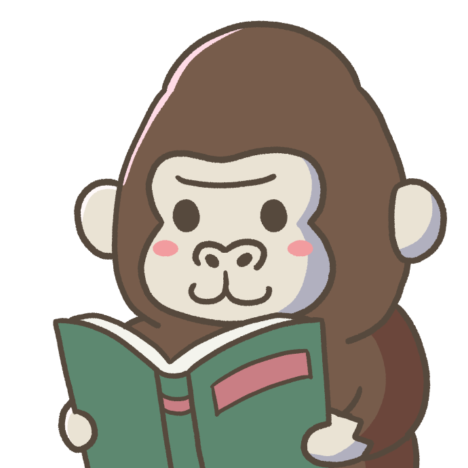
アウトプットをするしかない!簡単なものでいいから、今すぐ始めよう!
この記事では、読書のアウトプット方法について解説をします。
- 本を読んだときは自分が変われる気がするのに、結局行動に移せない
- 数日すると、読んだはずの本の内容を忘れてしまう
そんなことってありませんか?読書の知識が身につかない理由は、知識を定着させるためのアウトプットができていないからです。
本日読んだのは『自己肯定感を上げる OUTPUT読書術』。書評家YouTuberとして知られる、アバタロー氏の書籍です。最近読書のアウトプットをサボりがちなので、なんとか続ける方法が知りたいなと思って手に取りました。
もくじ
自己肯定感を上げる OUTPUT読書術ってどんな本?


読書の内容を忘れないだけでなくて、自己肯定感も上がるって本当ですか?
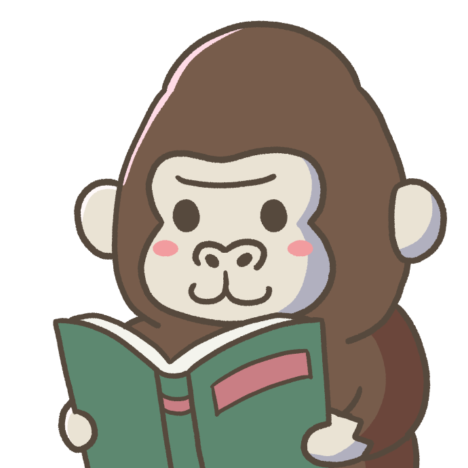
本当です。読書のアウトプットを通じて、自信を養えるんだ!
本書について一言で説明すると、「本を読んでアウトプットすることで、自己肯定感が上がり、人生を好転させる事ができる」という内容です。
あなたは、読了後にアウトプットしていますか?私は大学生ぐらいまでアウトプットをしていませんでした。読んだら読みっぱなし。そのせいで、せっかく学んだ内容を忘れてしまうこともあったと感じています。
アウトプットが知識の定着に役立つことは理解できます。しかし、なぜ自己肯定感を養うことにも繋がるのでしょうか?理由は三つあります。
- 書籍を通して考える力・説明する力が養われる
- 知識が自分の選択を後押ししてくれる
- アウトプットが増えていくことで小さな成功体験を積むことができる
ひとつずつ見ていきましょう。
書籍を通じて様々な思想・ノウハウに触れている人は、読書しない人に比べ、知識量が多いものです。知識は思考のための材料になります。
アウトプットによって知識を身につけることで、新たな視点で考えを巡らせることができるようになります。また、情報をわかりやすく整理し、他人に説明することにも役立ちます。
書籍を読んで知識が身につくと、根拠に基づいた意思決定ができるようになります。
例えば、新規事業を立ち上げるとき、転職や就職をするとき、投資をするとき・・・人生は選択の連続です。将来「あのとき、ああすればよかった・・・」と自分の選択を後悔すると、自己肯定感は下がります。
根拠を持って一つ一つの選択を吟味できれば、自信を持って選択できるようになります。
アウトプットは、成功体験を積むきっかけになります。
アウトプットを習慣化できれば、読書の記録は日々増えていくでしょう。自分が書いた「読書メモ」や「ブログの記事」や「Twitterの投稿」を振り返ることで、「こんなに沢山の書籍を読んだんだ!」と自信が生まれます。
ちなみにこれは、私も実感したことがあるんです。自信がなくなって死ぬほど落ち込んだときに、自分のブログの記事を読み返しています。「こんな馬鹿なこと書いてるけど、自分頑張ってるじゃん!」と前向きな気持ちになれるのでおすすめです。
読書のアウトプットにおすすめの方法3選
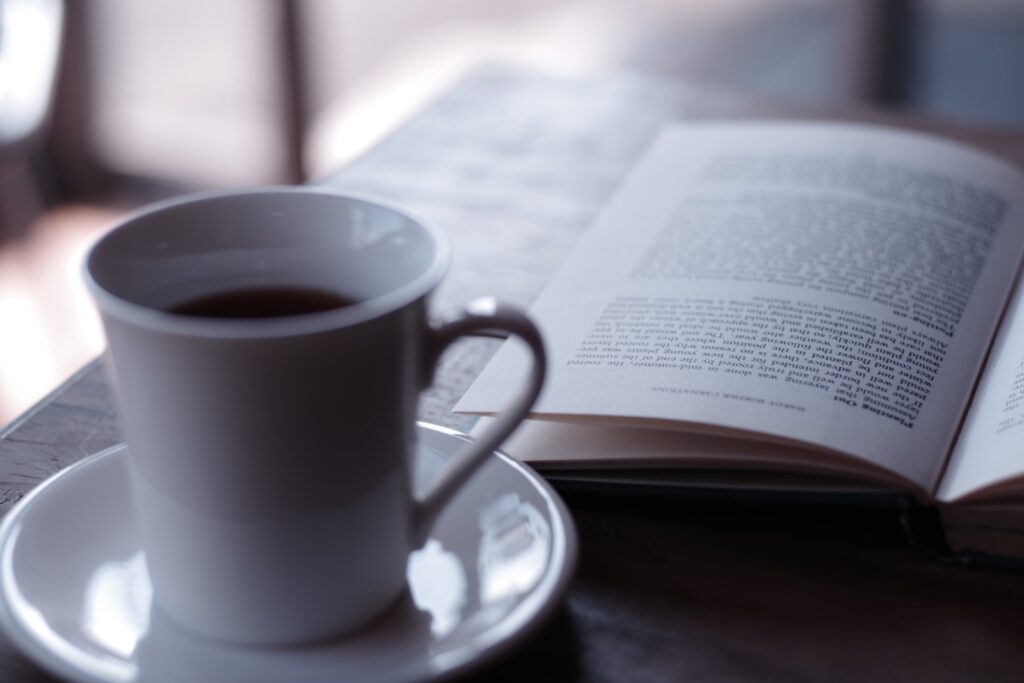

アウトプットが自己肯定感を高めるのに役立つのはわかった。
じゃあ、実際に何をすればいいの?
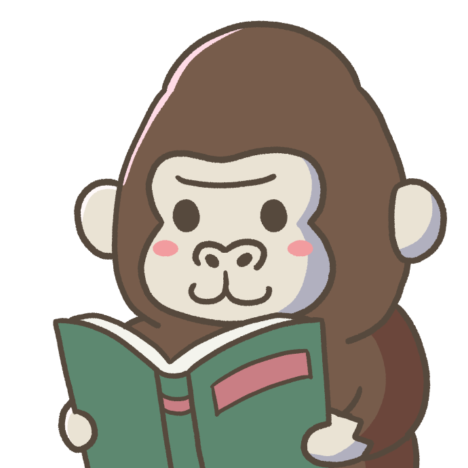
本書を読んで、私が取り入れたいと思ったやり方を3つ紹介します。
- 大事な情報の抜き出し:ふせんは三つに絞る!
- 情報の整理:A4用紙1枚に内容をまとめる!
- アウトプット方法:自分に適した方法を選び、楽しむ!
本に書いてある内容で、すべての情報が自分にとって有用であることは稀です。自分にとって大切な箇所と、そうではない箇所があります。「この情報は大切だぞ!」と思ったときに、ふせんを活用している人も多いのでは?
しかし、良いと思った箇所に次々ふせんを貼っていると、本がふせんだらけになって、結局どの部分が大切なのかわからなくなってしまうことがあります。
アウトプットのためには、まず自分が大切だと思う情報を絞ることが大事です。どの箇所が大切なのか、一目分かるほうが時間がかからず、楽です。
そこで本書では、「ふせんは3枚まで」というルールを推奨しています。
まず、1章ごとに貼るふせんは1枚だけ。本を読み終える頃には、章の数だけふせんが残っているはず。例えば、全5章構成の書籍なら5枚になります。
最後に、ふせんの中から特に大事なものを3つだけ残します。「全部大事な情報なのに・・・・!」と思っても、決断しましょう。
3つに絞ることができれば、情報を取捨選択する過程で自己決定する力が身につき、本当に大切な情報を頭に残すことができます。実際にアウトプットする際も、すべての内容をアウトプットすることは無理です。3つぐらいがちょうどよいな、と私も思います。
ふせんで情報の整理ができたら、その内容をA4用紙に書き出してみましょう。本の要約を作ると、本を読んで得た学びを編集し、自分にとってわかりやすくまとめる事ができます。
まとめる内容は、①筆者の主張②理由・根拠③再度筆者の主張 の順番で書き出すことがおすすめです。もしくは 本書の要点を列挙してまとめる という方法もあります。
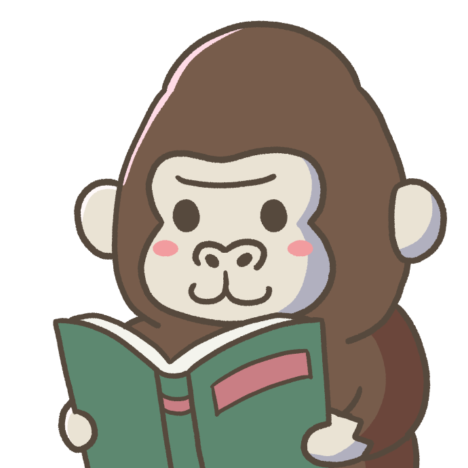
この作業は、まじでやるべき
私がまとめるときは、最初は何も見ずにA4用紙に内容を書き出しています。本の内容を思い出しながら書き、一通り書き出した後に、もう一度本を読みながら要約を手直ししてみるのです。
すると、自分が見落としていた学びに気づくことができます。
さて、肝心のアウトプット方法ですが、決まった方法はありません。自分に適した方法を見つけることが大事です。
・読書メモによる要約
・ノートに書く
・画像を作ってインスタグラムにUPする
・ブログに書く
・人に話す
・読書会に出席する・・・etc
どの方法を選ぶかは自由です。イラストが得意な人は、本の内容を画像にしたり、漫画にしたりすると面白いでしょう。私は絵がド下手なので文章でアウトプットしています。
どの方法を選ぶにせよ、一番大事なこと「楽しんでやる」ことです。続かないと意味がないということで、一番自分がやってて楽しいものにしましょう。
他の人のアウトプットを見ると落ち込んだり、こんな内容で公開するのが恥ずかしい・・・と思うかもしれませんが、気にする必要はありません。私も最初は書評を公開する際に「自分のクソを垂れ流す」気分になったものですが、1ヶ月もしたら慣れました。とにかく楽しく続けることが大切です。
アウトプットを継続して、読書の知識を自分のものにしよう!
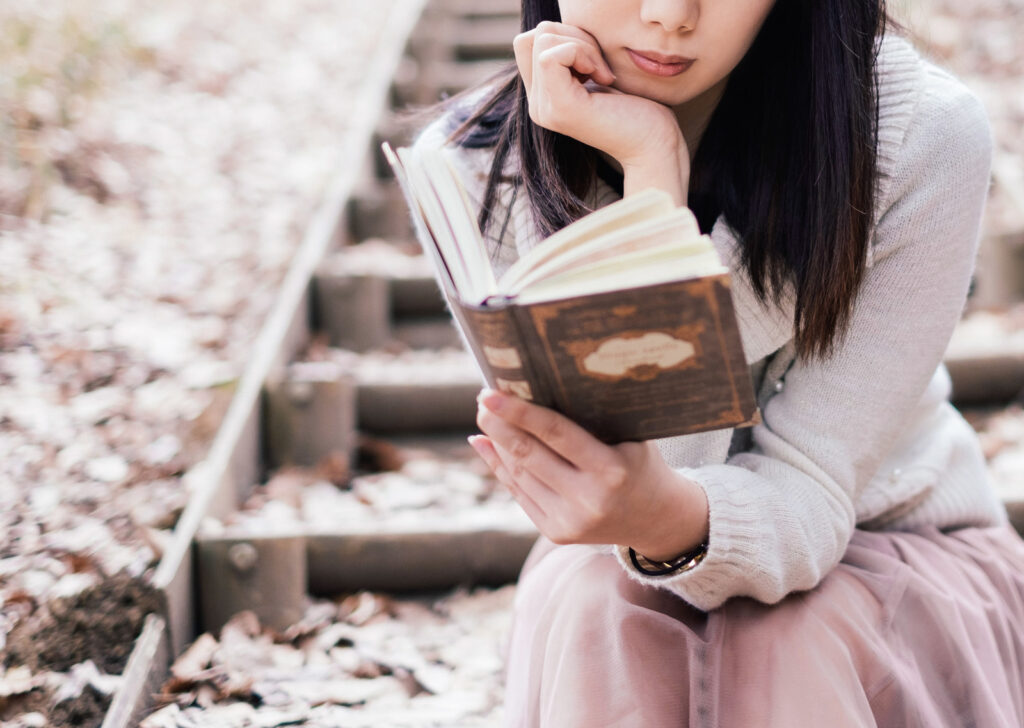
学習するとは、今までの自分を殺すこと
『勉強の哲学』という本で拝見した言葉です。知識を得ることは、今までの自分が知らない新たな世界に触れ、違う考え方ができることに繋がります。今の自分から脱皮して、新たな自分を見つけることになるでしょう。
自己肯定感とは、学習→脱皮の繰り返しによってしか高められないと思うのです。
本書は、読書のアウトプットを通じて自分の知識を増やし、自己肯定感を身につける方法を解説しています。本の読み方についてはかなり詳しく書かれており、普段本をあまり読まない人にとってもわかりやすい内容ではないでしょうか。
私もアウトプットをがんばります。いつか100記事を書いて、それが自分の土台になってくれたらいいなあ・・・と思うのです。